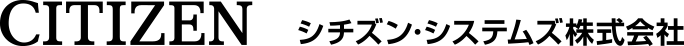体温が低いと何が起こる?要注意の症状や原因と対処方法とは
常に平熱が低い、熱を測ったらいつもより体温が低いと、なにか身体に問題が起きているのではないかと心配になるかもしれません。
「冷えは万病のもと」とはよく聞きますが、体温が低いとどのような影響があるのでしょうか?
今回は低体温と冷え症の違いや低体温の影響、体温が低くなる原因とその対処方法について解説します。

- 【目次】
- 1.体温35.5~36.0℃以下は低体温
- 低体温とは?冷え症との違い
- 低体温が身体に与える悪影響
- 2.体温が低くなる原因
- ストレス
- 急激な体重の減少
- 筋肉量の減少
- 加齢による衰え
- 甲状腺ホルモンの減少
- 長時間の低温環境
- 3.体温が低いときに注意すべき症状
- 初期症状(体温35.0~36.5℃程度)
- 軽度の症状(体温34.0~35.0℃程度)
- 中~重症の症状(体温32.0~34.0℃程度)
- 5.体温アップを目指そう!低体温予防につながる生活習慣
- 食事
- 運動
- 入浴
1.体温35.5~36.0℃以下は低体温
平熱は人によって異なるとはいえ、あまりに体温が低いと身体の機能に影響が及ぶことがあります。
- 低体温とは?冷え症との違い
低体温とは、深部体温(脳や内臓など身体内部の体温)が低い状態を指します。明確な定義はありませんが、体温計での測定結果が35.5~36.0℃以下の人は、低体温の可能性があるので要注意です。
一方、冷え症は、深部体温は下がっていなくても手足などに部分的な冷えを感じる状態です。体全体の温度が低くなる低体温とは異なります。
- 低体温が身体に与える悪影響
低体温は免疫力の低下につながります。身体の免疫機能が低下するため、細菌やウイルスなどの病原体に感染しやすくなります。
また、内臓が冷えることで消化不良や体力の低下、食欲不振が起こります。自律神経の乱れによる血行不良になり、冷え症も同時に感じるかもしれません。
低体温が続くと、集中力や思考力の低下にまでつながります。さまざまな健康被害が生じるため、適切な対処が必要です。
2.体温が低くなる原因
低体温は、さまざまな要因で引き起こされます。以下のように、日常生活で見られる環境も低体温を招く原因となるため注意しましょう。
- ストレス
自律神経は交感神経と副交感神経からなり、この2つがバランスを保つことで体内環境を整えています。しかし、強いストレスを感じると自律神経が乱れて体温調節機能が働かなくなり、低体温症を引き起こす可能性があります。
- 急激な体重の減少
激しい運動や過度なダイエットで急激に体重が減ると、身体の熱を生む新陳代謝を鈍らせます。体温を上げる働きが悪くなり、低体温の原因となるのです。
- 筋肉量の減少
筋肉には身体の熱を生み出す熱産生という働きがあります。運動不足や加齢によって筋肉量が減ると、体温を維持できなくなり徐々に体温も低い状態になってしまうでしょう。
- 加齢による衰え
加齢にともない体温が低下することがわかっています。筋力低下による基礎代謝の低下、食事量や活動量の減少によるエネルギー消費量の低下が主な原因です。他にも、体温調節機能の衰えも背景にあります。
- 甲状腺ホルモンの減少
甲状腺ホルモンの減少も体温低下の原因になります。甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝を促し、熱を生む働きがあります。しかし、病気などで甲状腺ホルモンが減少すると、この働きが弱まり、体温が下がってしまいます。
- 長時間の低温環境
長時間の低温環境にさらされると体温が下がることがあります。寒さによって筋肉が凝り固まると、熱をうまく生み出せなくなり、体温が下がってしまいます。雪山や冬の屋外などの特殊な環境下に限らず室内での発症例も増えているため注意が必要です。
3.体温が低いときに注意すべき症状
低体温の症状は非常にゆっくりと現れるため、本人も周りの人も気づきにくいことが特徴です。少しでも異変を感じたら迅速な対処が求められます。
低体温の症状を3段階に分けてみていきましょう。
※参照元:「低体温症の主な症状と初期症状|体温ごとの変化と治療方法を説明」(健達ねっと by メディカル・ケア・サービス (株))
- 初期症状(体温35.0~36.5℃程度)
- 寒気や震えが出始める
- 指の動きが鈍くなる
- 動作がぎこちない
- 皮膚の感覚が麻痺しはじめる
低体温の初期症状には、熱を発生させるための身体の震えが見られます。少しずつ動きが鈍化し始め、手足や指の動きがゆっくりになる、皮膚の感覚が麻痺するなどさまざまな異変が出始めます。
- 軽度の症状(体温34.0~35.0℃程度)
- 歩行でよろける
- 転倒しやすくなる
- うわごとを言う
体温がさらに低下すると、身体の動きが鈍くなり、転んだりよろけたり歩行に障害が出ます。うわごとなど意識にも問題が出始めます。
- 中~重症の症状(体温32.0~34.0℃程度)
- 震えが減少する
- 歩けない
- 頻呼吸
- 意識障害がはじまる
重症になると震えは減少し、歩行が困難になります。意識があっても、会話が成り立たず支離滅裂な様子が見られます。32.0℃以下の体温は、身体の硬直が始まり、意識低下や錯乱、不整脈のリスクが高まります。命の危険がかなり高い、生存ラインぎりぎりの状態です。
4.体温が低いときの対処方法
低体温の症状がみられたら、迅速な対応が大切です。シバリング(震え)が始まり低体温を自覚したら、冷えた身体を温めて対処します。次のような方法で身体を温めるといいでしょう。
- 温かい場所に移動する
- 暖房で室温を上げる
- 衣類や電気毛布で体を保温する
- 食事や飲み物で栄養と水分を補給する
身体が濡れている場合は、濡れた服を脱ぎ身体を拭いてから温めることが大切です。帽子やマフラーなどで保温するのもいいでしょう。
体温を上げるエネルギーとして食事の摂取もおすすめです。甘いものや白米、パンなどの炭水化物は体温アップにより効果的です。また、体内に十分な水分を補給することで、血流が良くなり、体温も上昇します。温かい飲み物やカロリーのある飲み物がベストです。
「家庭で対処できるか不安」「病院に行った方がいいか判断が難しい」という場合は、早めの受診を検討しましょう。
5.体温アップを目指そう!低体温予防につながる生活習慣
健康を維持するためには低体温の原因となる生活習慣を取り除き、日頃から予防に努めることが大切です。ここでは食事・運動・入浴の3つの習慣から、低体温を防ぐポイントを紹介します。
- 食事
- 身体を温める食材を摂る
- たんぱく質を摂る
- 三食しっかり食べる
身体を温める食材には発酵食品や根菜、温かい汁物などがあります。たんぱく質も体温を上昇させるため、卵や納豆、味噌汁、焼き魚などの和食メニューがおすすめです。栄養バランスの取れた食事を3食きちんと食べて、身体の体温調整機能を整えましょう。
- 運動
- ウォーキングやスクワットなどを行い筋肉の代謝を上げる
- 体温の低い朝に運動する習慣をつける
運動は熱を生み出す筋肉を維持・増強し、代謝アップに役立ちます。本格的な運動が難しくても、ウォーキングやスクワットなど簡単な運動でも有効です。体温が低い朝の時間帯に、身体を動かす習慣をつけると温まりやすい身体作りにつながります。
- 入浴
- 毎日入浴する
- 40℃のお湯で10分程度つかる
身体の内部は気づかないうちに冷えているものです。身体全体を芯から温めるには湯船に肩から浸かって入浴することがおすすめです。40℃のお湯に10分ほど浸かると体温が1℃上がるといわれています。
6.まとめ
低体温とは身体内部の体温が低い状態のことです。明確な定義はありませんが、熱を測ったときに35.5~36.0℃以下だと低体温の可能性があります。
低体温の原因には、ストレスによる自律神経の乱れ、体重の減少、運動不足や加齢による筋肉量の低下、低温環境に長時間身を置くことなどがあります。
低体温の初期症状には身体の震えや動きの鈍化、皮膚の感覚の麻痺などが挙げられます。症状が進むと震えすら止まり、歩けなくなったり意識を失ったりして命の危険が生じます。これらの症状はゆっくりと現れるため、少しでも異変を感じたら体を温め、医療機関を受診しましょう。
また、日頃から食生活や運動、入浴の習慣で体温を上げる対策を行うことが大切です。