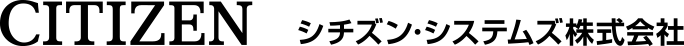妊活にかかるお金・法規制
妊活を始めるにあたって、まず気になるのが「費用がどれくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。
2022年からは不妊治療の一部が保険適用となり、経済的負担が軽減されつつありますが、治療内容や選択によっては自費となるケースもあります。また、各自治体で実施されている助成金制度が利用できるかもしれません。
本記事では、妊活にかかる費用の目安や、保険・助成金制度の活用方法について、わかりやすく解説します。

- 【目次】
- 1.2022年から妊活が保険適用に
- 保険適用の条件
- 2.保険適用の妊活費用
- タイミング法
- 人工授精(AIH)
- 体外受精(IVF)
- 顕微授精(ICSI)
- 精巣内精子採取術(TESE)
- 3.保険適用外の妊活費用
- 先進医療
- 自費の薬代・文書料
- サプリメント・代替療法
1.2022年から妊活が保険適用に
妊活にかかるお金として非常に重要な要素として、2022年4月から不妊治療の多くが保険の対象となったことが挙げられます。
これまでは全額自己負担だった治療費が保険適用によって3割負担となり、経済的なハードルが大きく下がりました。これにより、高額な費用のために治療を諦めていたカップルにとって、妊娠に向けた選択肢が広がる大きな変化となりました。
保険適用の対象となるのは、タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精など、一般的に行われている不妊治療の方法です。採卵や受精、胚移植といった工程ごとに診療報酬が設定されており、それに基づいて保険が適用されます。
- 保険適用の条件
保険を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
・女性の年齢が治療計画作成時点で43歳未満
・胚移植の場合:施術回数が上限を上回っていない
(40歳未満:1子につき6回/40歳以上43歳未満:同3回まで)
こうした制限はあるものの、年齢条件を満たせば、基本的な治療のプロセスを保険で受けることができる仕組みとなっています。(2025年掲載時点)
2.保険適用の妊活費用
国内外で広く効果が認められている一般的な不妊治療には保険が適用されます。
ここでは、代表的な妊活の治療法ごとに保険診療でかかる費用の目安をご紹介します。
- タイミング法
費用:排卵1周期あたり数千円~2万円
タイミング法は、排卵の時期に合わせて性交のタイミングを調整する方法です。自分で排卵日を予測して実施することもでき、その場合、費用はほとんどかかりません。自分でタイミング法を行い、効果が出なければ医師に相談する流れが一般的です。
保険適用で行う場合の費用は、診察内容やホルモン検査の有無、排卵誘発剤を使用するかどうかによって変わってきます。
- 人工授精(AIH)
洗浄・濃縮した精子を排卵日に合わせて子宮に注入する方法。保険診療では1回あたり5,000円程度。
不妊治療としては、比較的費用負担が少ない方法の一つといえるでしょう。
- 体外受精(IVF)
費用:1回あたり12,000円程度
体外受精は、卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療です。
採卵・受精・胚移植といった工程を含むため、自費で受けると20~40万円以上かかることもあります。保険適用による費用軽減の効果が非常に大きい治療法です。
- 顕微授精(ICSI)
費用:1回あたり1~4万円程度
顕微授精は、顕微鏡を使って1つの精子を直接卵子に注入する方法で、特に重度の男性不妊に効果的です。
自費の場合は7~19万円ほどかかるのが一般的とされています。
- 精巣内精子採取術(TESE)
費用:6万円程度~
精液に精子が確認できない場合には、精巣から直接精子を採取する「精巣内精子採取術(TESE)」という手術が行われます。
simple-TESEと呼ばれる比較的シンプルな施術では1回6~8万円程度、より高度な「顕微鏡下精巣内精子回収術(MD-TESE)」の場合は10~20万円が相場とされています。
3.保険適用外の妊活費用
効用が十分に認められていない先進医療や民間療法は保険適用外となるケースがあります。予算を相談しながら必要に応じて取り入れましょう。
- 先進医療
- IMSI(高倍率顕微授精)
費用:1万円程度~
通常より高倍率の顕微鏡を使用して、より形態の良い精子を選んで顕微授精を行う方法です。受精率や妊娠率の向上を目的としており、特に重度の男性不妊に用いられることがあります。 - PICSI(ヒアルロン酸選別法)
費用:2万2,000円程度~
精子がヒアルロン酸に結合する性質を利用して、成熟度の高い精子を選別する方法です。自然に近い選別方法とされ、受精卵の質の向上が期待されています。 - タイムラプス培養
費用:3万円程度~
胚の発育を時間経過ごとに記録する特殊な培養法で、より良好な胚を選ぶために利用されます。培養器内で観察できるため、胚へのストレスが少ないのも特徴です。 - 内膜擦過(スクラッチ)
費用:1万円程度~
子宮内膜に軽い刺激を与えることで着床率の向上を期待する方法です。着床不全が続いているケースで行われることが多く、比較的簡便な処置である点も特徴です。 - EMMA・ALICE検査
費用:5万6,000円程度
子宮内の細菌環境や慢性子宮内膜炎の有無を調べる検査です。着床環境の改善を目的としており、不妊の原因を特定するための一助となります。 - ERA検査
費用:13万7,000円程度
子宮内膜が胚の着床に最も適したタイミング(着床の窓)を調べる検査です。体外受精での着床不全が続く場合に有効とされ、移植の時期をより的確に判断できます。
- IMSI(高倍率顕微授精)
- 自費の薬代・文書料
診断書や治療証明書などの発行には、1通あたり数千円の費用が必要です。
また、妊娠判定後に処方される薬は、保険の対象外となるケースが多く、1回で2万円以上かかることもあります。
- サプリメント・代替療法
栄養補助を目的としたサプリメントの摂取や、鍼灸などの代替療法も利用されています。
鍼灸は1回あたり約1万円、週に複数回通う場合は月あたり数万円になることもあります。
妊活としてこれらを推奨するケースもありますが、費用は保険適用の対象外となる点に注意が必要です。
4.妊活で利用できる助成金制度
妊活では、不妊治療に保険が適用できるほかにも自治体ごとに助成金が支給されるケースもあります。
例えば、東京都では「不妊検査等女性」として、超音波検査・内分泌検査・精液検査などの不妊検査に要した費用を最大5万円まで助成する制度があります。また、保険適用外の先進医療についても同様に助成金制度が設けられています。
自治体によって助成金制度は異なるため、詳しくはお住まいの地域のHPをご確認ください。
5.まとめ
妊活には一定の費用がかかりますが、すべてを自己負担するわけではありません。保険適用が拡大されたことで、タイミング法や人工授精、体外受精といった不妊治療は一定条件のもとで負担軽減が可能になりました。さらに、先進医療や不妊検査などの費用も、助成制度を活用することで一部カバーできる場合があります。
妊活では、ある程度費用の目安を理解したうえで治療法を選択することが大切です。費用面まで含めてパートナーや産婦人科と相談し、自分のペースで妊活を進めていきましょう。