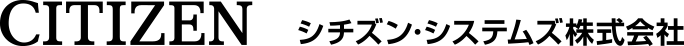妊活前のワクチン接種
妊活中は体調管理に加え、感染症への備えも欠かせません。妊娠中に感染すると母体や胎児に大きな影響を及ぼす疾患に対しては、事前にワクチン接種で予防することが大切です。
この記事では、妊活中に接種が推奨されるそれぞれのワクチン・感染症の特徴について分かりやすく解説します。

- 【目次】
- 1.妊活中に接種すべきワクチン①MMRワクチン
- 麻疹とは
- 風疹とは
- おたふく風邪とは
- 抗体検査について
- 2.妊活中に接種すべきワクチン②水痘ワクチン
- 水痘とは
- 抗体検査について
- 3.妊活中に接種すべきワクチン③HPVワクチン
- HPVとは
- 4.妊活中に接種すべきワクチン④B型肝炎ワクチン
- B型肝炎とは
1.妊活中に接種すべきワクチン①MMRワクチン
MMRワクチン(麻疹・風疹・おたふく風邪の三種混合ワクチン)は、妊娠中にかかると重篤な合併症を引き起こす可能性がある3つの感染症を防ぐためのワクチンです。通常は1回の接種で効果が得られますが、抗体が不十分な場合は2回目の接種が勧められます。
接種後は最低2か月間の避妊が必要となるため、妊活スケジュールとあわせて計画的に接種することが大切です。
MMRワクチンで予防できる疾患である麻疹・風疹・おたふく風邪について詳しく見ていきましょう。
- 麻疹とは
「麻疹ウイルス」にかかることで発症する感染症で、「はしか」とも呼ばれます。肺炎などの合併症を引き起こしやすいことで知られており、妊娠中に麻疹に感染すると、母体に肺炎や脳炎といった合併症が起こることがあります。
さらに、流産や早産、低出生体重児のリスクも高まるため、妊娠前にしっかり予防することが重要です。
- 風疹とは
「風疹ウイルス」によって引き起こされる感染症で、発熱やリンパ節の腫れのほか、発疹が出るのが特徴的です。
妊娠初期で風疹に感染した場合、胎児が先天性風疹症候群(CRS)を引き起こす可能性があります。
先天性風疹症候群は心疾患、視覚・聴覚障害、精神発達遅延など、重い後遺症をもたらす疾患であり、抗体を持っていない場合はワクチンによる予防が推奨されます。
- おたふく風邪とは
おたふく風邪は「ムンプスウイルス」と呼ばれるウイルスへの感染が原因となって起こる病気で、頬のあたり(耳下腺)の腫れが特徴的です。
6歳までの子どもがかかることが多い感染症ですが、抗体を持っていない場合は大人でも感染する可能性があります。
妊娠中に感染すると、流産や早産のリスクを高めるとされています。また、母体の体調に大きな負担がかかることもあるため、事前の予防が望まれます。
- 抗体検査について
これら3つの感染症はどれも一度感染した人は一生免疫が持続するため、基本的には「一度もその病気にかかったことがない人=抗体がない人」が対象のワクチンになります。
現在幼少期の接種が義務化されているMRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)の効果は10年程度、任意接種のおたふく風邪ワクチンは20~30年程度の効果が認められています。
つまり、幼少期のワクチン接種歴に関わらず、過去にこれらの感染症にかかった経歴がない場合は抗体がない(弱まっている)状態となっている可能性があるため注意が必要です。
「過去にかかった経験があるか分からない」という方は、まず抗体検査を受けることをおすすめします。現在、多くの自治体で風疹の抗体検査が無料で提供されており、麻疹やおたふく風邪も自費で抗体検査を受けることができます。
2.妊活中に接種すべきワクチン②水痘ワクチン
妊娠を計画している方にとって、水痘(水ぼうそう)への感染は胎児や母体に深刻な影響を及ぼす可能性がある危険な感染症です。
一度水痘にかかったことがある方は抗体があるため基本的に対策する必要はありませんが、抗体がない方は妊活中に水痘ワクチンを接種することが強く推奨されます。
- 水痘とは
水痘は子どもがかかるイメージが強い病気ですが、大人が感染すると重症化しやすく、特に妊娠中に感染すると胎児に重大な影響を及ぼす可能性があります。
胎児に生じる可能性がある「先天性水痘症候群」では、四肢の形成異常、眼の異常、中枢神経の障害などがみられることがあります。また、妊婦自身も肺炎などにより重症化するリスクが高くなるため、妊娠前の予防が大切です。
- 抗体検査について
水痘に対する抗体があるかどうかは血液検査で簡単に確認できます。上記でご紹介した麻疹・風疹・おたふく風邪と合わせて「4種抗体検査」を行うのもおすすめです。
妊活の初期段階で抗体をチェックし、ワクチンの必要性があるか確認しておくとよいでしょう。
3.妊活中に接種すべきワクチン③HPVワクチン
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種も検討しておきたい予防策のひとつです。HPVは子宮頸がんの原因となるウイルスであり、ワクチンによる予防が非常に有効とされています。
1回目の接種から2か月後に2回目、6か月後に3回目を接種する流れで、全3回の接種を完了することで十分な予防効果が期待できます。
日本では現在15歳以上の女性に接種が推奨されており、接種を逃した方向けに平成9年度生まれ~平成20年度生まれの女性かつ、2022年4月~2025年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種した方が公費でのキャッチアップ接種の対象となっています。※
公費接種の対象ではない方も、自費での摂取が可能です。
こちらも妊娠中の接種は推奨されていないため、接種を希望される場合は妊娠前に接種スケジュールを完了しておくことが大切です。
※記事執筆時点(2025年4月)の情報です。現在の正しい情報は省庁・地方自治体のホームページをご確認ください。
- HPVとは
HPVは主に性的接触を通じて感染するウイルスで、一部の型に感染すると子宮頸がんや肛門がん、咽頭がんなどのリスクが高まることが知られています。
HPVワクチンを接種することで、子宮頸がんを起こしやすい型のHPVへの感染リスクを大幅に低減できるとされています。
4.妊活中に接種すべきワクチン④B型肝炎ワクチン
B型肝炎ワクチンは新生児に対して定期接種が行われていますが、大人でも抗体がない場合には任意で接種することができます。ワクチンは通常3回接種が基本とされており、1回目の接種から4週間後に2回目、さらに20~24週間後に3回目を接種するスケジュールとなっています。
ワクチン接種は妊娠中には推奨されていないため、妊娠を希望する段階での計画的な接種が必要となります。接種前に血液検査で抗体の有無を確認することができます。
- B型肝炎とは
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)によって引き起こされる感染症で、血液や体液を介して感染します。感染すると急性肝炎として発症する場合があり、一部は慢性化して肝硬変や肝がんへと進行することもあります。
母体がB型肝炎に感染している場合、出産時に赤ちゃんに感染が及ぶリスクがあります。妊活中に抗体の有無をチェックし、必要に応じてワクチンを接種しておくことが望ましいでしょう。
5.妊活中に接種すべきワクチン⑤インフルエンザワクチン
妊活中にインフルエンザワクチンを接種しておくことは、妊娠中の健康を守るために重要です。
普段から感染に気をつけている方も多いかと思いますが、妊娠中は免疫力が低下しているため、インフルエンザに感染しやすく重症化しやすい傾向があります。また流産や早産の増加など、胎児にも影響を与える可能性があるともいわれています。
そのため、妊娠中の感染を防ぐ予防策として妊活中の段階からワクチンを接種しておくことが望ましいでしょう。
ただしインフルエンザワクチンは「不活化ワクチン」と呼ばれるもので、その他の「生ワクチン」とは異なり、妊娠中でも安全に接種できるとされています。ですから、厳密には妊娠の有無にかかわらず、流行期に合わせて接種が推奨されるワクチンだといえるでしょう。
6.まとめ
妊活中のワクチン接種は、未来の赤ちゃんと自分自身を守るための大切な準備です。感染症の中には妊娠中の感染が深刻な影響を及ぼすものもあるため、事前に抗体検査を受け、必要に応じて早い段階でワクチンを接種しておくことが推奨されます。
妊娠を望むタイミングに合わせて、計画的に対策を進めていきましょう。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。