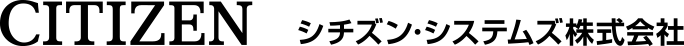男性の不妊について
不妊の原因は女性にあると思われがちですが、実際には男性側にも原因があるケースが少なくありません。近年では男性の不妊への理解が進み、治療方法が発展してきました。
女性のことだけでなく男性の不妊についても正しく知識をつけることで、妊活を円滑に進めることができるでしょう。
この記事では、男性不妊症の基本的な知識や主な検査方法、治療法などを詳しく解説します。

- 【目次】
- 2.男性不妊症の原因
- 造精機能障害
- 性機能障害
- 精路通過障害
- 無精子症
- 3.男性不妊症の検査方法
- 精液検査
- 超音波検査
- 血液検査(ホルモン検査)
- 性感染症検査
- 遺伝子検査
- 4.男性不妊症の治療方法
- 生活習慣の見直し
- 漢方・サプリメント
- 薬物療法
- 手術
- 生殖補助医療(ART)
1.男性不妊症とは
男性不妊症とは、妊娠を望むカップルが1年間避妊せずに性交渉を続けても妊娠に至らない場合に、その原因が男性側にある状態を指します。
WHO(世界保健機関)の調査によれば、不妊症全体の約48%には男性側の要因が関与しているとされており、男性不妊症が決して珍しいものではないことが分かります。
男性不妊症は女性の不妊に比べて認識されにくい傾向にありますが、妊活においては大きな影響をもたらす可能性があるといえます。
2.男性不妊症の原因
男性不妊症にはさまざまな原因がありますが、中でも精子の状態や性機能の異常が主な要因とされることが多い傾向です。
代表的な原因について詳しく見ていきましょう。
- 造精機能障害
最も多く見られる原因が、精巣内で精子をつくる機能が低下する「造精機能障害」です。厚生労働省研究班の調査(2015)の調査によれば、男性不妊症の約82.4%を占めるとされています。
この「造精機能障害」には精子の数が少ない「乏精子症」や精子の運動率が低い「精子無力症」といった状態が含まれます。先天的な要因だけでなく、生活習慣や加齢の影響、原因不明のケースも少なくありません。
- 精索静脈瘤
造精機能障害のなかでも原因として割合が高いのは「精索静脈瘤」です。これは精巣上部にある精索静脈が肥大化する疾患で、正常男性の約15%、男性不妊症患者の40%にみられるといわれています。
精索静脈が肥大化すると温度の高い血液が精巣の温度を上げ、精子の働きを悪くする可能性があります。精索静脈瘤があるからといって必ずしも不妊になるわけではありませんが、妊活においては手術による治療が推奨されます。
- 精索静脈瘤
- 性機能障害
性機能障害は勃起・射精の機能不全が原因で性交に問題が生じる状態を指します。
具体的には大きく「勃起障害(ED)」「射精障害」に分類されます。
- 勃起障害(ED)
勃起障害は性交を行うのに十分な勃起を維持できない状態を指し、特に心因性の要因が多い障害です。
妊活においては排卵日のタイミングで性交を行う「タイミング法」が男性にとってプレッシャーになり勃起障害を引き起こしている可能性があります。ストレス・プレッシャーの要因が明確な場合、薬物療法のほか要因となっている環境を変えれば改善するケースも見られます。
- 射精障害
射精障害は射精そのものに関わる問題であり、射精のメカニズムに障害が生じることで不妊症の原因となる症状です。
性行為中に射精ができない状態である「膣内射精障害」、射精時に精液が膀胱へ逆流してしまう「逆行性射精」などがあり、勃起障害と比較すると治療が難しい傾向があります。
- 勃起障害(ED)
- 精路通過障害
精子が精巣から外に出る道筋が閉塞している場合も不妊症の原因となります。
精管が詰まっている、もしくは精液中に精子が含まれない場合、精巣内で精子が正常に作られていても、射精時に精子が出てこないことがあります。
こうした精路通過障害は手術で解消できる場合もありますが、かなり専門的な治療が必要となります。
- 無精子症
無精子症とは、射精された精液の中に精子がまったく含まれていない状態を指します。男性不妊症の中でも比較的多く見られ、妊活においては大きな課題となる症状です。
この状態に至る主な原因は上記で紹介した造精機能障害と精路通過障害の2種類がありますが、いずれのケースでも適切な検査によって原因を明らかにしたうえで早い段階で治療を検討することが重要です。
3.男性不妊症の検査方法
男性不妊症の診断には、複数の検査を組み合わせて行うことが重要です。精子の状態や精巣の構造、ホルモンバランスなどを多角的に確認することで、原因を明らかにして適切な治療方針を立てることができます。
具体的には以下のような方法で検査を行うのが一般的です。
- 精液検査
精液検査はもっとも基本的かつ重要な検査で、精液量や精子の濃度、運動率、正常形態の割合などを総合的に評価します。それぞれの検査項目で定められた基準値を下回る場合、自然妊娠が困難であると判断されます。
男性不妊を取り扱っている産婦人科や泌尿器科で検査が可能なほか、最近ではスマートフォンを使って自宅で簡易的に精液検査ができるキットも登場しています。
- 超音波検査
超音波検査では精巣の大きさや精索静脈瘤の有無を調べます。
特に精索静脈瘤は造精機能に悪影響を及ぼす可能性があるため、精巣の血管の太さや血液の逆流の有無などを確認して正確に検査を行う必要があります。
- 血液検査(ホルモン検査)
血液検査では、精子の生成に関わるホルモンのバランスを調べるために行われます。
主に、FSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)、テストステロン(男性ホルモン)などが測定対象です。この検査によってホルモンの異常が見られた場合は、内服薬や注射による治療で改善を試みるのが一般的です。
- 性感染症検査
クラミジアや淋菌といった性感染症は、男性不妊の原因になることがあります。加えて、B型肝炎・C型肝炎・梅毒・HIVといった病気への感染も確認します。
万が一検査によって感染があれば、妊活開始前に治療を行う必要が出てきます。
- 遺伝子検査
無精子症や乏精子症の男性に対しては、染色体異常などの有無を調べる遺伝子検査を行うことがあります。
これにより、根本的な原因の特定や将来的な治療選択の判断材料になります。
4.男性不妊症の治療方法
男性不妊症の治療は、原因や状態に応じてさまざまな方法があります。生活習慣の改善から医療的なアプローチまで、複数の手段を組み合わせることで妊娠の可能性を高めることが期待されます。
男性不妊症と診断された場合は医師の判断のもとで以下のような治療を行うのが一般的です。
- 生活習慣の見直し
不規則な生活やストレス、肥満、喫煙などは、精子の質に悪影響を与える要因とされています。栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を取り入れることで、全身の健康とともに精子の質も改善が期待できます。
また、精巣は熱に弱いため、長時間の入浴やサウナ、ノートパソコンを膝の上で使用するなどの高温環境を避けることも大切です。
- 漢方・サプリメント
医学的に明確な効果が立証されているわけではありませんが、漢方薬や抗酸化作用を持つサプリメントが医師の指導のもとで処方され、補助的に用いられることがあります。
精子の数や精子運動率に問題がある場合は漢方やサプリメントの服用を相談してみるのも一つの手です。
- 薬物療法
勃起障害や射精障害がある場合には、医師の診断のもとバイアグラやシアリスといった薬剤によって勃起機能を改善する治療が行われるのが一般的です。
またホルモン分泌に問題がある場合には、クロミフェン法やGnRH療法などのホルモン補充療法により造精機能の改善を目指します。
- 手術
特定の疾患が原因で不妊症となっている場合には、手術による治療が選択されることがあります。
代表的なのは「精索静脈瘤」で、手術を通じて造精機能の改善を目指します。
- 生殖補助医療(ART)
射精や造精機能に問題がある場合、人工授精や体外受精(IVF)といった生殖補助医療(ART)が必要となることがあります。
さまざまな要因により精子が十分に採取できない場合でも、精巣から直接精子を採取する方法を用いて体外受精を行うことが可能です。採取した精子を用いれば、精子数が少ないケースや運動率が低い場合でも妊娠の可能性を高めることができます。
5.まとめ
男性不妊症は決して珍しいものではなく、全体の不妊症のうち約半数が男性側にも原因があるとされています。
造精機能障害や性機能の問題、精路の障害など原因はさまざまですが、適切な検査と治療によって改善が見込めるケースも多くあります。
生活習慣の見直しをはじめ、必要に応じて薬物療法や手術、生殖補助医療の選択肢も視野に入れ、パートナーと協力しながら進めることが何よりも大切です。妊活を行う場合はなるべく早期に男性側の検査も行いましょう。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。