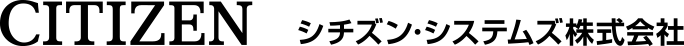妊活での男性側のサポートの重要性
妊活は女性だけのものではなく、男性の協力が重要です。妊娠の成立には、男女双方の健康状態や生活習慣が影響を与えるため、パートナーと協力しながら取り組むことが大切です。
男性側が妊娠に関する知識を深め、食生活や生活習慣を見直すことは、妊娠の可能性を高めるだけでなく、夫婦の絆を深めることにもつながります。また、不妊の原因は男性側にもあることが多く、必要に応じて検査を受けることも大切です。
本記事では、妊活で男性ができるサポートや、男性不妊について詳しく解説します。

- 【目次】
- 1.妊活で男性ができるサポート
- 妊娠についての理解
- 妊活の進め方やライフプランを話し合う
- コミュニケーションを取る
- 食生活の改善
- 生活習慣の改善
- 禁煙
- 2.男性不妊について
- 精子の異常
- 性機能障害
1.妊活で男性ができるサポート
妊活は夫婦で協力して取り組むことが大切です。しかし、実際のところは女性が中心になりがちで、男性が具体的にどのようにサポートすればよいのか分からないこともあるかもしれません。
ここでは、妊活を進めるうえで男性ができる具体的なサポートについて解説します。
- 妊娠についての理解
妊娠のメカニズムに関する知識は、大きな身体の変化を経験する女性に比べ、男性の方が乏しいことが多いものです。そのため、夫婦で妊娠についての知識を共有し、コミュニケーションをとることが大切です。
まずは妊娠に関する書籍を読んだり、信頼できる妊活サイトの記事を共有したりすることで、理解を深めるとよいでしょう。
例えば、卵子は基本的に増えることはなく加齢に伴って少しずつ減少していくことや、年齢や生活環境によって卵子の質が変化することを知らない男性はかなり多いのではないでしょうか。妊活を早く行わなければならない背景や、パートナーのサポートが必要となる理由などをしっかりと理解し、夫婦で共有することが大切です。
- 妊活の進め方やライフプランを話し合う
妊活を円滑に進めるためには、夫婦でライフプランや治療の進め方について話し合うことも重要です。
妊活の方法として、「自然妊娠を希望する」「体外受精などの不妊治療を積極的に進める」などさまざまな選択肢があります。どんな方針で進めるかお互いの意見をすり合わせておくことで、妊活が長引いた際にもトラブルが起きにくくなります。
また、妊娠後の不安を取り除くためにも、子どもを何人希望するか、育休の取得や育児の分担についても妊娠前に話し合っておくことが望ましいでしょう。スタート時点だけでなく、妊活の過程で定期的にお互いの気持ちを確認し合うことが大切です。
- コミュニケーションを取る
妊活はときにデリケートな話題となることがあり、特に女性は周囲の言葉に敏感になってしまうこともあるでしょう。例えば、妊活をしている状況で親族や友人からの「子どもはまだ?」といった言葉をかけられ、プレッシャーに感じる方も少なくないと思います。
そういった悩みを一人で抱え込まないよう、周囲とのコミュニケーションをサポートしたり、それぞれが持つストレスやプレッシャーを理解しあったりと、普段から意思疎通を図ることが大切です。
- 食生活の改善
妊娠しやすい体を作るためには、バランスの取れた食事が重要です。特定の食材を必ず摂取する必要はありませんが、朝昼晩の食事を規則正しくとり、炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラルを意識することが大切です。
妊活中に特に摂取したい栄養素として、亜鉛と葉酸が挙げられます。
亜鉛は精子の運動率を向上させる働きがあり、不足すると精子の質が低下する可能性があります。牡蠣やレバーに多く含まれるため、積極的に摂取するとよいでしょう。
葉酸は男女どちらの体にとっても重要な栄養素であり、精子のDNAを保護する働きを持ちます。ほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれますが、食事だけで十分に摂取するのが難しい場合は、サプリメントを活用するのも良い方法です。
- 生活習慣の改善
妊活を成功させるためには、健康的な生活習慣を整えることが大切です。
十分な睡眠は、体と心の健康を維持するために不可欠です。最低でも1日6時間は睡眠時間を確保すると、体調を整えやすくなります。
また、適度な運動はストレスの軽減にもつながります。ウォーキングやランニング、ジムでのトレーニングなど、無理のない範囲で運動習慣を取り入れるとよいでしょう。運動が苦手な人は、パートナーと一緒に楽しめるスポーツやストレッチを取り入れることで継続しやすくなるかもしれません。
- 禁煙
喫煙は流産や死産のリスクを高める可能性があるため、妊活を始める際には禁煙することが望ましいでしょう。また、たばこの煙は血流を悪化させ、精子の質の低下やDNAの損傷を引き起こすことも知られています。
女性が禁煙することはもちろん、男性もなるべく喫煙せず受動喫煙を防ぐことも大切です。男性が率先して禁煙に取り組むことで、妊娠しやすい環境を整えることができるでしょう。
2.男性不妊について
「男性は不妊治療に関係がない」と誤解されることも少なくありませんが、妊娠は男女双方の健康状態に影響されるものであり、不妊の原因が男性側にあることも少なくありません。
WHO(世界保健機関)の調査によると、不妊の原因の約半分が男性にあるとされ、男性側の問題によって妊娠が難しくなる状態を「男性不妊」と呼びます。
男性不妊は生活習慣の見直しや治療によって改善できる場合もあるため、気になる症状がある場合は早めに医師に相談し、適切な診断・検査を受けることが大切です。
- 精子の異常
精子の形成や運動性に問題があると、受精が難しくなります。厚生労働省の「我が国における男性不妊に対する検査・治療に関する調査(2015年)」によると、男性不妊の原因の82.4%は「造精機能障害(精子を正常に作る機能が低下している状態)」だといいます。
造精機能障害は具体的に以下のような異常が挙げられます。
・精子が全く作られない(無精子症)
・精子の数が少ない(乏精子症)
・精子の運動率が低い(精子無力症)
・奇形の精子が多い(精子奇形症)
精子を作る機能に異常があると、性交渉を重ねても妊娠に至らないことが多くなります。特に無精子症は100人に1人の割合で発生するとされ、精液中に精子が全く存在しない状態です。
- 性機能障害
性機能障害とは、勃起や射精が正常に行われない状態を指し、不妊の原因となることがあります。主な原因は「器質的要因」と「心理的要因」に分けられます。
器質的要因:高血圧や糖尿病などの生活習慣病、ホルモン異常などによるもの
心理的要因:ストレスや緊張によるもの
最近では妊活により「排卵日付近に性交をしなければならない」というプレッシャーが影響し、勃起不全や射精障害を引き起こすケースも増えています。
3.必要に応じて男性不妊の検査を行おう
男性の不妊検査は精液の状態を調べる「精液検査」が基本となります。精液検査では専用の容器に採取した精液を分析し、精液量や精子の数、運動率、形態、DNAの状態を確認することで、精子の質を判断できます。
精子の状態は個人差が大きく、体調や生活習慣によっても影響を受けるため、検査結果にばらつきが出ることがあります。そのため、妊活を行う上では何回か検査を実施するのが一般的です。
必要に応じて男性側も検査を受けることがスムーズな妊娠につながる一歩となります。検査を希望する場合や男性目線で気になる点がある場合は医師に相談してみましょう。
男性不妊について相談する場合は男性不妊外来のある産婦人科、もしくは泌尿器科を受診するとスムーズです。女性が既に産婦人科へ通っている場合はまず同じ病院で相談してみるのもよいでしょう。
4.まとめ
妊活は夫婦で取り組むものだからこそ、男性の理解と協力が欠かせません。妊娠の仕組みを知り、パートナーと話し合いながら、食生活や生活習慣の改善を意識することが、妊娠しやすい環境を整える第一歩になります。
また、不妊の原因は男性側にもあるとされており、精子の質や性機能の問題が影響することもあります。必要に応じて検査を受け、健康管理を意識しましょう。
妊活はすぐに結果が出ない場合もありますが、長期間にわたって続く可能性があるからこそ夫婦で支え合いながら取り組んで無理なく続けることが大切です。自分たちに合った方法を見つけ、前向きに妊活を進めていってください。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。