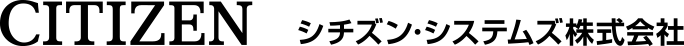月経の量、色、不正出血と経血の見分け方、おりもの変化、女性疾患
生理の経血やおりものの状態は、ホルモンバランスや子宮の健康状態を知る重要な手がかりになります。生理周期に伴う変化は自然なものですが、経血の量や色の異常、おりものの異常が続く場合は、ホルモンの乱れや婦人科系疾患が関係していることもあります。
妊活のステップを踏むにあたっては、生理に関する基礎知識を知って対策を進めていくことが大切です。本記事では、生理やおりものの変化や不正出血の特徴、そしてその原因となりうる疾患について詳しく解説します。

- 【目次】
- 1.生理・おりものの状態から分かること
- 経血の量
- 経血の色
- おりものの色と状態
- 透明・乳白色
- 黄色
- 茶色・ピンク色
- 2.不正出血と生理の違い
- 不正出血は受診すべき?
- 3.不正出血の原因
- ホルモンバランスの乱れ
- 婦人科疾患
- 排卵出血
- 低用量ピルの服用
- 4.生理の異常・不正出血の原因となる女性疾患
- 子宮筋腫
- 子宮内膜症
- 子宮腺筋症
- 子宮頸管ポリープ・子宮内膜ポリープ
- 子宮頸がん・子宮体がん
- 萎縮性腟炎(閉経後の不正出血)
- 腟炎・細菌性腟症
1.生理・おりものの状態から分かること
生理の経血やおりものの状態は、ホルモンバランスや子宮の健康状態を知る手がかりになります。
経血の量や色の変化、おりものの性状の違いには、自然な生理的変化もあれば、身体の不調を示していることもあります。異常が見られた場合は自分で判断せず、必要に応じて医師に相談することが大切です。
- 経血の量
生理の経血量は通常20~140mLの範囲とされており、これを超える場合は「過多月経」、少ない場合は「過少月経」とされます。
- 過多月経
経血量が140mL以上と多い場合、子宮筋腫、子宮腺筋症、ホルモン異常が関係していることがあります。
ナプキンを1時間おきに交換しなければならない、夜用ナプキンでも昼間に漏れるなどの場合は過多月経とみなされますので注意が必要です。
- 過少月経
経血量が20mL以下と少なくナプキンがほとんど汚れないような場合は過少月経とされます。
この場合もホルモンバランスの乱れや、卵巣機能の低下が原因となっている可能性があります。
- 過多月経
- 経血の色
生理の経血の色は、体の状態やホルモンバランスによって変化します。生理周期の中で色が変わるのは通常の生理現象ですが、異常が続く場合は婦人科疾患が関係していることもあります。
- 鮮血(明るい赤)
生理の初期に見られる新鮮な血液で、健康な状態を示しています。子宮内膜が剥がれたばかりの血液がスムーズに排出されているため、酸化する前の明るい赤色になります。
ただし、生理周期に関係なく鮮血が続く場合は、不正出血の可能性があり、ホルモンバランスの乱れや子宮の異常が関係していることもあります。
- ピンク色の経血
経血に粘液が混ざることで薄まるとピンク色になることがあります。これは生理の始まりや終わりに見られることが多く、一時的な変化であれば問題ありません。しかし、長期間ピンク色の出血が続く場合は、貧血やホルモンバランスの乱れが関係していることがあります。
また、排卵期に軽い出血が起こる「排卵出血」でもピンク色の経血が見られることがあります。排卵出血は生理とは異なり、ごく少量で数日以内に止まるのが一般的です。
- 黒っぽい経血
生理の終盤になると、経血の排出が遅くなり、膣内に長く滞留することで酸化が進み、黒っぽい色になることがあります。これは正常な生理の過程であり、特に問題はありません。
しかし、黒い経血が生理期間の大半を占める場合や、生理とは関係なく黒っぽい出血が続く場合は、子宮内膜症やホルモンの異常が関係している可能性があります。
- おりものの色と状態
おりものは、膣内を清潔に保ち、感染を防ぐために分泌される粘液です。その量や形状はホルモンバランスの変化に影響を受け、生理周期に応じて変化します。特に排卵期には量が増え、粘り気が強くなるのが特徴です。
しかし、異常に増え続ける、粘度が極端に強くなる、においが強くなる、色が変化するなどの症状が見られる場合は、ホルモンバランスの乱れや感染症の可能性も考えられます。日常的におりものの状態を観察し、異常が続く場合は早めに婦人科を受診することが大切です。
- 透明・乳白色
通常のおりものの色であり、健康な状態を示します。排卵期には透明で粘り気が強くなり、排卵後は白っぽくなることが一般的です。
- 黄色
生理前になるとホルモンの影響でおりものが黄色っぽくなることがあります。
通常は問題ありませんが、強いにおいやかゆみを伴う場合や、濃い黄色のおりものが出ている場合は、膣内で雑菌が繁殖している可能性があるため、注意が必要です。
- 茶色・ピンク色
生理直前や生理後、排卵後に見られることがあり、わずかな経血が混ざることで変色することが多いです。このような変化は不正出血の一種とみなされますが、生理周期に伴うものであれば基本的に問題はありません。
ただし、頻繁に茶色やピンク色のおりものがみられる状態が続く場合は、ホルモンバランスの乱れや婦人科系疾患が関係している可能性があります。婦人科への受診を検討しましょう。
- 鮮血(明るい赤)
2.不正出血と生理の違い
不正出血と生理はどちらも膣からの出血ですが、発生する原因や特徴には違いがあります。
生理はホルモンの働きによって周期的に起こる子宮内膜の剥離による出血です。通常、一定の周期で訪れ、数日間続きます。一方、不正出血は子宮内膜が部分的に剥がれた状態であることが多く、生理の周期とは関係なく突然起こることがあります。
- 不正出血は受診すべき?
不正出血が1回のみ、または複数回でもごく少量であれば、一時的なホルモンバランスの乱れや、排卵期や生理前後の自然な出血の可能性が高く、緊急性は低いと考えられます。
ただし、出血量が多い場合は貧血や体調不良につながり、症状が重い場合は輸血が必要になるケースもあるため、早めに受診することが大切です。また、少量であっても長期間続く場合や、痛みを伴う場合は、婦人科を受診し、適切な診断・検査を受けることをおすすめします。
3.不正出血の原因
不正出血が起こる原因はさまざまですが、大きく分けるとホルモンバランスの乱れによるものと、婦人科系の疾患によるものがあります。
- ホルモンバランスの乱れ
ホルモンバランスが乱れると、子宮内膜が不安定になり、不正出血が起こることがあります。このような不正出血は「機能性出血」と呼ばれます。
特に思春期や更年期は、ホルモンの分泌が不安定になりやすいため、不正出血が起こりやすい時期です。また、精神的・身体的なストレスがホルモンの分泌に影響を与え、不正出血を引き起こすこともあります。
- 婦人科疾患
子宮や膣の病気が原因で出血が起こる場合、これを「器質性出血」と呼びます。これらの疾患が進行すると、生理以外の時期にも出血が見られることがあります。
不正出血の原因となる婦人科疾患については、後の項目で詳しく説明します。
- 排卵出血
排卵期には、ホルモンの急激な変化が起こるため、少量の出血が見られることがあります。これを「排卵出血」と呼びます。
通常は1~2日程度の少量の出血で、特に問題はありません。ただし、頻繁に排卵出血が起こる場合は、ホルモンバランスが不安定になっている可能性があるため、注意が必要です。
- 低用量ピルの服用
低用量ピルを服用している場合、ホルモンバランスの変化により、服用初期に不正出血が見られることがあります。これは一時的なもので、通常2~3ヶ月ほどで落ち着くことがほとんどです。
低用量ピルは、医師の診察を受け、処方箋をもらうことで入手できます。自己判断での服用や中断はホルモンバランスを乱す原因となるため、適切な指導のもとで使用することが大切です。
長期間にわたって出血が続く場合、出血量が多い場合は、何らかの体調変化が関係している可能性もあります。気になる症状があるときは、早めに医師に相談するようにしましょう。
4.生理の異常・不正出血の原因となる女性疾患
ここまで解説してきたように、生理の異常や不正出血は婦人科系の疾患が関係している場合もあります。
少しでも気になる点がある場合は早めに婦人科を受診しましょう。ここでは不正出血の原因となる主な女性疾患についてご紹介します。
- 子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮の筋層に発生する良性の腫瘍であり、女性ホルモン(エストロゲン)の影響を受けて成長します。
筋腫の位置や大きさによっては、生理の経血量が増加する過多月経や、生理期間の延長が見られることがあります。出血が8日以上続くことや、生理とは関係なく不正出血が起こることもあります。
また、筋腫が大きくなると、子宮が膀胱や直腸を圧迫し、頻尿や便秘の原因となるケースもみられます。
- 子宮内膜症
子宮内膜症は、本来子宮の内側にあるはずの子宮内膜に似た組織が、卵巣や腹膜など子宮以外の場所に発生し、増殖・剥離を繰り返す疾患です。
20代~40代の女性に多く見られ、生理のたびに強い下腹部痛や腰痛が起こるのが特徴です。また、経血量が増える過多月経や、生理以外の時期の不正出血が見られることもあります。
症状が悪化すると不妊の原因となることもあるため、生理痛がひどい場合は早めの受診が推奨されます。
- 子宮腺筋症
子宮腺筋症は、子宮の筋層内に子宮内膜組織が入り込み、増殖する疾患です。
子宮筋腫と似た症状があり、特に生理痛が強くなる傾向があります。鎮痛薬が効きにくいほどの痛みを伴うこともあり、経血量が非常に多くなり、貧血を引き起こすこともあります。
また、生理期間が通常より長くなることがあり、出血がダラダラと続くのが特徴です。進行すると、子宮が肥大し、月経不順が起こることもあります。
- 子宮頸管ポリープ・子宮内膜ポリープ
子宮頸管や子宮内膜に発生する良性の腫瘍で、通常は無症状ですが、性交後や運動後に出血が見られることがあり、生理とは異なるタイミングで不正出血が起こることがあります。
また、ポリープの位置や大きさによっては、経血量が増え、過多月経を引き起こすこともあります。ポリープが大きくなると、妊娠しづらくなる原因になることもあります。
- 子宮頸がん・子宮体がん
子宮頸がんはHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が主な原因で、子宮体がんはエストロゲンの影響によって発生します。
どちらも初期は自覚症状が少ないですが、進行すると生理とは関係のない不正出血が見られることがあります。
特に、閉経後の出血は注意が必要で、子宮体がんの可能性があるため、早期の診察が望まれます。進行すると、おりものの量が増えて水っぽい性状に変化することがあります。
- 萎縮性腟炎(閉経後の不正出血)
閉経後、エストロゲンの分泌が低下することで膣粘膜が薄くなり、炎症を起こしやすくなることがあります。膣内が乾燥し、わずかな刺激で少量の不正出血が起こることがあり、性交時に痛みを感じることもあります。
閉経後の不正出血は、子宮体がんの可能性もあるため、注意が必要です。
- 腟炎・細菌性腟症
他人からの感染や免疫力の低下などが原因で膣内の細菌バランスが崩れて膣炎になり、不正出血が発生することがあります。
腟内の粘膜が傷つきやすくなるため少量の出血が見られることがあり、膣炎の種類によってはおりものの量が増えたり、色が黄色や緑色に変化したりすることもあります。
膣炎はかゆみや痛みを伴うことが多く、放置すると症状が悪化するため、早めの治療が必要です。
5.まとめ
生理やおりものの変化は、ホルモンバランスや子宮の健康状態を反映する大切な指標です。経血の量や色、おりものの状態を日頃から把握しておくことで、身体の変化に早く気づくことができます。
不正出血や生理の異常は一時的なホルモンバランスの乱れが原因のこともありますが、何らかの婦人科疾患が関係している可能性もあります。特に妊活を行う方にとっては早めの治療が重要です。
気になる症状があるときは自己判断しないで医師と相談し、適切な診断・検査を受けるようにしましょう。体のサインを見逃さず、ご自分に合ったケアを心がけましょう。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。