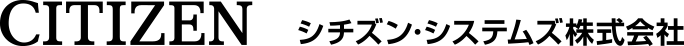月経(生理)に伴う体の変化
生理前や生理中には、ホルモンバランスの変化によりさまざまな症状が現れることがあります。体の冷えや倦怠感、肌の不調、気分の浮き沈みなどを感じていらっしゃる女性も多いのではないでしょうか。これらの変化は不妊にも関連する場合があるので、特に妊活を進めている方は必要に応じてしっかり対処していくことが重要です。
本記事では生理前・生理中に表れる変化や妊活との関連性、不調を和らげる対策について解説します。自分の体の変化を理解し、妊活をスムーズに進めるための参考にしてください。

- 【目次】
- 1.生理前に表れる変化
- 眠気やだるさ
- 腹痛や腰痛
- 頭痛
- 吐き気
- 食欲の増加
- 体重増加やむくみ
- おりものの変化
- 微熱が続く
- 肌荒れやニキビ
- イライラや情緒不安定
- 2.生理中に表れる変化
- 出血
- 腹痛・腰痛
- 頭痛
- 貧血
- 冷えやむくみ
- 肌荒れやニキビ
- 倦怠感・眠気
- イライラや気分の落ち込み
- 3.生理の症状と不妊の関連性
- 子宮内膜症
- 4.生理前・生理中の症状を緩和する対策
- 体を温める
- 食生活の改善
- 適度な運動
- 十分な睡眠を確保する
- ストレスを減らす
- 鎮痛薬を適切に使う
- 婦人科を受診する
1.生理前に表れる変化
生理前の体の変化は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンの影響を受けています。エストロゲンは排卵前に多く分泌され、気分の安定や肌の調子を整える役割を果たします。一方、プロゲステロンは排卵後に分泌が増え、基礎体温を上昇させたり、体内に水分をため込みやすくしたりする働きがあります。これらのホルモンの変動によって、心や体にさまざまな変化が起こるのです。
また、ホルモンバランスの変化に伴って生理前にはさまざまな不調が現れることがあります。人によって個人差はありますが、日常生活に影響を及ぼすレベルで症状が重たい場合は月経前症候群(PMS:Premenstrual Syndrome) と呼ばれます。月経前症候群(PMS)は、生理開始の数日前から現れ、生理が始まると軽減または消失するのが特徴です。
以下のような症状が強く、日常生活に支障をきたしている場合は、産婦人科を受診することも検討しましょう。
- 眠気やだるさ
生理前の黄体期(アンバランス期)にはプロゲステロンの影響で体温が高くなり、睡眠の質が低下しやすくなります。そのため、日中に強い眠気やだるさを感じることがあります。
- 腹痛や腰痛
生理前になると、プロスタグランジンという物質が分泌され、子宮の収縮を促します。その影響で、生理前から腹痛や腰痛が起こることがあります。また、黄体ホルモンの作用で腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなることもあります。
- 頭痛
生理前はエストロゲンの分泌量が減少します。急激な分泌量の減少が起こると脳内の血管が拡張し、片頭痛が発生しやすくなります。
生理前後に起こる「月経関連片頭痛」は通常の片頭痛よりも痛みが強く、長引くことがあるのが特徴です。
- 吐き気
プロスタグランジンの分泌が増えることで、子宮だけでなく胃や腸の筋肉も刺激され、吐き気を感じることがあります。
- 食欲の増加
プロゲステロンの影響で血糖値が不安定になりやすく、甘いものを欲することがあります。また、血糖値の低下により空腹を感じやすくなるため、生理前に食欲が増すことが多いです。
- 体重増加やむくみ
生理前にはプロゲステロンの影響で体内に水分が溜まりやすくなり、むくみや体重の増加が起こりやすくなります。
さらに、腸の動きが鈍くなって便秘が起こることも、体重が増える一因となります。
- おりものの変化
生理前になると、おりものの量が増え、白っぽくなり、粘り気が強くなることがあります。また少量の経血が混ざることで、黄色や茶色っぽく見えることもあります。
- 微熱が続く
生理前は高温期にあたり、基礎体温が上昇するため、37℃前後の微熱が続き、体がだるく感じることがあります。
- 肌荒れやニキビ
エストロゲンの分泌が減少し、皮脂の分泌が増えるため、肌荒れやニキビができやすくなります。特に、顎や口の周りに吹き出物ができることが多いとされています。
- イライラや情緒不安定
エストロゲンが減少すると、精神を安定させる働きを持つセロトニンの分泌も低下するため、イライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなったりします。
ホルモンバランスの変化により集中力が低下し、仕事や勉強に身が入らなくなることもあります。
2.生理中に表れる変化
生理中はホルモンバランスの変化により、さまざまな症状が現れることがあります。腹痛や腰痛、頭痛、倦怠感などを感じる人が多く、場合によっては日常生活に影響を及ぼすこともあります。
生理中の症状には個人差があります。無症状の人もいれば、強い倦怠感や痛みに悩まされる人もいます。特に、強い痛みや不調が続く場合は、単なる生理痛ではなく「月経困難症」と診断されることもあるので、自身の体調をよく観察しながら、無理のない過ごし方を心がけることが大切です。
症状には個人差がありますので、体調がすぐれないときは必要に応じて受診を検討しましょう。
- 出血
生理中は子宮内膜が剥がれ落ち、経血として排出されます。正常な生理周期は25~38日で、出血期間は3~7日が一般的です。経血量には個人差がありますが、20~140mlの範囲が正常とされています。
- 腹痛・腰痛
生理中に分泌されるプロスタグランジンは、子宮の収縮を促す働きがありますが、過剰に分泌されると強い生理痛を引き起こすことがあります。
また、腸の動きにも影響を与え、下痢や便秘の原因となることがあります。腰痛も子宮の収縮による影響で発生することが多いです。
- 頭痛
生理が始まると、エストロゲンの分泌が急激に低下するため、血管が拡張しやすくなり、片頭痛が起こりやすくなります。生理中に起こる「月経関連片頭痛」は通常の片頭痛よりも症状が長引きやすく、痛みが強い傾向にあります。
- 貧血
生理中は経血とともに鉄分が失われるため、鉄欠乏性貧血になることがあります。貧血になると、めまい、立ちくらみ、動悸、顔色の悪化、倦怠感などの症状が現れます。
特に経血量が多い場合は、貧血が進行しやすくなるため注意が必要です。
- 冷えやむくみ
生理中はホルモンバランスの変化により、血流が悪くなりやすくなります。そのため、手足の冷えやむくみを感じることが多くなります。
冷えやすい体質の人は意識的に体を温める工夫をするとよいでしょう。
- 肌荒れやニキビ
生理中はホルモンバランスが乱れ、皮脂の分泌が増加するため、肌荒れやニキビができやすくなります。特に顎やフェイスラインに吹き出物ができることが多いとされています。
- 倦怠感・眠気
生理中はプロゲステロンの影響が続くため、基礎体温が高めの状態が続き、体がだるく感じることがあります。また、血行不良により疲れやすくなり、強い眠気を感じることもあります。
- イライラや気分の落ち込み
生理前と同じく、エストロゲンの低下によって脳内のセロトニン(精神を安定させる物質)の分泌が減少するため、イライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなったりします。
ホルモンバランスの影響により、精神的に不安定になることがあるため、リラックスできる時間を意識的に確保することも大切です。
3.生理の症状と不妊の関連性
生理に伴う強い痛みや異常な症状は、ホルモンバランスの乱れや婦人科系の疾患が原因となっている可能性があり、不妊につながることがあります。特に、子宮や卵巣に関わる疾患が隠れている場合、放置すると妊娠しにくくなることがあるため、早めの対処が重要です。
- 子宮内膜症
子宮内膜症は、本来子宮内腔にのみ存在するはずの子宮内膜に似た組織が、卵巣、腹膜、腸などの子宮外に発生し、増殖する疾患です。これらの組織は生理周期に合わせて増殖・剥離を繰り返しますが、通常の生理のように体外へ排出されないため、炎症や癒着を引き起こすことがあります。
子宮内環境の悪化や炎症の影響で、子宮内膜症患者の30~50%が不妊を経験するとされています。生理痛が重い、出血量が多いなど、子宮内膜症を疑う症状がみられる場合は早めに婦人科を受診して適切な治療を受けることが大切です。
4.生理前・生理中の症状を緩和する対策
生理前や生理中に起こる不調は、ホルモンバランスの変化による影響が大きく、人によって症状の出方も異なります。
症状を和らげるためには、生活習慣を見直し、自分に合った対策を取り入れることが大切です。無理のない範囲でできることから始め、心と体の負担を減らしていきましょう。
- 体を温める
生理前や生理中は血行が悪くなりやすく、冷えによって生理痛や腰痛が悪化することがあります。カイロや湯たんぽでお腹や腰を温めると血流が改善され、痛みが和らぎやすくなります。
また、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体が温まるだけでなく、リラックス効果も期待できます。
- 食生活の改善
鉄分やビタミンB群、カルシウム、マグネシウムを含む食品を積極的に摂ると、PMSや生理痛の症状が軽減しやすくなります。鉄分は貧血予防に、ビタミンB群はホルモンバランスの調整に役立ちます。
また、カフェインや塩分の過剰摂取はむくみや血行不良を引き起こすことがあるため、控えめにするのが望ましいでしょう。
- 適度な運動
軽いストレッチやウォーキングは血流を促進し、ホルモンバランスを整えるのに役立ちます。
ヨガやピラティスなどの穏やかな運動もリラックス効果があり、PMSの緩和に効果が期待できます。ただし、激しい運動はかえって体に負担をかけることがあるため、無理のない範囲で取り入れることが大切です。
- 十分な睡眠を確保する
生理前はホルモンバランスの影響で睡眠の質が低下しやすくなります。そのため、意識的にリラックスする時間を作ることが重要です。
寝る前にスマホやPCの使用を控える、温かい飲み物を飲むなど、安眠につながるリラックスタイムを作るとよいでしょう。
- ストレスを減らす
ストレスはホルモンバランスを乱し、生理前のイライラや月経前症候群(PMS)の悪化につながることがあります。好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、ゆっくりとした時間を過ごすことで、気持ちが落ち着くこともあります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、心と体をリラックスさせることが大切です。
- 鎮痛薬を適切に使う
生理痛の原因の一つはプロスタグランジンの分泌です。プロスタグランジンは子宮の収縮を促して経血を排出しやすくする働きがありますが、過剰に分泌されると強い痛みを引き起こすことがあります。
イブプロフェンやロキソプロフェンなどの鎮痛薬には、プロスタグランジンの分泌を抑える作用があるため、痛みが軽減しやすくなります。生理痛がひどい場合は、無理をせずに鎮痛薬を適切に使用することが大切です。
- 婦人科を受診する
生理痛が年々悪化している、鎮痛薬を飲んでも効かない、生理前の症状が重く日常生活に支障をきたす場合は、子宮内膜症などの婦人科系疾患が隠れている可能性があります。こうした症状がある場合は産婦人科を受診し、適切な診断・検査を受けることが大切です。
医師と相談しながら、必要に応じてホルモン療法や低用量ピルなどの治療法を検討すると、症状が緩和しやすくなります。
5.まとめ
生理前や生理中の症状は、ホルモンバランスの変化によって起こり、人によってその程度や種類は異なります。強い痛みなどの症状は日常生活の負担になるだけでなく、不妊につながる可能性もあるため、早めに婦人科を受診して適切な診断・検査を受けることが大切です。
また、日々の生活の中で、体を温めたり、栄養バランスの良い食事を心がけたりすることで、症状を和らげることができます。
自分に合った対策を見つけ、できるだけ快適に過ごせるように工夫していきましょう。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。