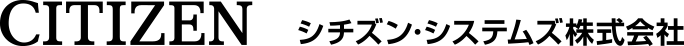月経(生理)周期について基礎知識
生理周期は女性の心身の状態をつかさどる大切な要素ですが、「なんとなく知っている…」というだけで、意外とよくご存じない方も多いのではないでしょうか。
特に妊活中の方は、基礎体温の計測やホルモンバランスの乱れを見つけるのに不可欠な生理周期についてしっかり頭に入れておきましょう。女性だけでなく、男性も生理周期の仕組みを知っておくことが大切です。
本記事では生理周期にまつわる基本的な知識を分かりやすく解説します。

- 【目次】
- 1.生理周期(月経周期)の仕組み
- 生理周期(月経周期)とは
- 生理周期の数え方
- 2.生理周期の基礎①生理期(月経期)
- 生理期(月経期)の身体の変化
- 3.生理周期の基礎②卵胞期(キラキラ期)
- 卵胞期の身体の変化
- 4.生理周期の基礎③排卵期
- 排卵期の身体の変化
- 5.生理周期の基礎④黄体期(アンバランス期)
- 黄体期の身体の変化
- 6.月経・生理周期に関するトラブル
- 生理周期が短い・長い
- 生理周期がバラバラ
- 生理期間が長い・短い
- 経血が多い・少ない
1.生理周期(月経周期)の仕組み
女性の身体において生理は一定の周期であらわれるため、その周期を「生理周期(月経周期)」と呼びます。
- 生理周期(月経周期)とは
厳密には「出血が始まる月経開始日」から「次の月経の前日までの期間」を指して生理周期と言います。おおよそ25~38日の範囲が正常な生理周期といわれています。
生理周期は大きく「排卵期」「黄体期」「生理期(月経期)」「卵胞期」の4フェーズに分かれており、女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌バランスによって身体のコンディションが調整されていきます。
- 生理周期の数え方
生理周期は複数の生理開始日間の日数の平均値をとります。一般的には、直近3~6回の日数を測ることが推奨されています。
例えば直近の生理開始が3日前、31日前、59日前、87日前だった場合、生理開始日間の平均はおよそ28日、つまり生理周期も28日ということになります。
2.生理周期の基礎①生理期(月経期)
生理周期の各フェーズについて詳しく見ていきましょう。生理(月経)とは、卵胞期から黄体期にかけて徐々に分厚くなっていった子宮内膜が剥がれ落ち、血液とともに排出される現象です。出血が始まった日から生理期(月経期)にカウントし、正常な生理期(月経期)の期間(生理期間)は3~7日間とされています。
この時期からプロゲステロンの分泌量が減少するため、基礎体温は低くなります。
- 生理期(月経期)の身体の変化
下腹痛、腰痛、腹部膨満感、嘔気、頭痛、疲労・脱力感、食欲不振、イライラ、下痢、憂鬱などの症状がみられることがあり、これらの症状が日常生活に支障をきたしている場合は月経困難症と診断されます。
月経困難症は子宮内膜症、子宮筋腫などの疾患が原因となっているケースもあるため、症状が重い場合は診断をおすすめします。
3.生理周期の周期の基礎②卵胞期(キラキラ期)
卵胞期は卵巣内で卵胞が成熟する時期で、エストロゲンが多く分泌されます。
このエストロゲンの作用で生理中薄くなった子宮内膜が再び厚くなっていき、再度排卵・妊娠への準備が始まります。
- 卵胞期の身体の変化
一般的に卵胞期は心身ともに最も安定している時期です。肌や髪の状態もよくなり、気持ちも落ち着いてポジティブに過ごせる人が多いといわれています。
卵胞期はホルモンの分泌バランスによりむくみが取れやすく、比較的痩せやすくなるといわれています。
4.生理周期の基礎③排卵期
排卵期は卵子が卵胞から卵管へ出てくる時期で、エストロゲンが多く分泌されてホルモンバランスが大きく変化します。
プロゲステロンの働きで排卵期の途中(排卵の後)から基礎体温が高くなります。
女性の排卵時期に関する法則を考案した「オギノ式」によれば、排卵予定日は「前回の生理開始確定日―生理周期日数」で大まかに計算できます。
- 排卵期の身体の変化
排卵期はホルモンの急激な変化が起こるため、冷えやむくみ、腹痛、だるさといった体調不良が起こりやすくなります。
排卵のとき下腹部に痛みがあらわれたり、不正出血が起こったりするケースもあります。
排卵日前後は睡眠を十分に取って、生活リズムを整えましょう。カラダを冷やさないようにしたり、ストレスを発散したりする対策も効果的です。
5.生理周期の基礎④黄体期(アンバランス期)
黄体期は排卵の後、卵胞が黄体に変化する時期です。体温を上げる働きを持つプロゲステロンを多く分泌するため、基礎体温が上昇していきます。また、排卵期に引き続きエストロゲンも分泌されます。
プロゲステロンとエストロゲンの作用で子宮内膜は厚く柔らかくなり、妊娠に適した環境を整えていきます。この際、子宮内膜には着床に備えて受精卵のための水分や栄養素がため込まれるようになります。
ちなみに黄体期はばらつきがありますがおおよそ14日程度で、人によっては排卵期と時期が重なることがあります。
黄体期までに妊娠が成立しなかった場合、黄体ホルモンと卵胞ホルモンの血中濃度は低下して月経が始まります。
- 黄体期の身体の変化
生理周期で考えると黄体期は月経が始まる前の段階で、女性ホルモンの影響でカラダもココロも不安定になりやすくなります。具体的には、腰痛や頭痛、肩こり、ニキビなどの症状が出やすいといわれています。
精神的にはイライラや憂うつ感、眠気、不眠、過食などの症状が出やすくなるほか、乳房が膨らんだり、触れると痛んだりする変化が現れることもあります。
また黄体期には体に水分をため込みやすくなるため、むくみが生じやすくなります。中には急に体重が増えたり、人によっては頭痛が出たり、おなかが張ったりといった症状がみられることもあります。
これらの不快な症状が日常生活に支障をきたす場合はPMS(月経前症候群)、特にこころの症状が重い場合はPMDD(月経前不快気分障害)と診断されるケースもあります。月経前の症状にお悩みの方は、妊活の有無にかかわらず一度婦人科に相談してみましょう。
6.月経・生理周期に関するトラブル
月経と生理周期について、以下のようなトラブルがみられる場合には注意が必要です。
- 生理周期が短い・長い
生理周期が24日以内の場合「頻発月経」、39日以上の場合は「稀発月経」と呼ばれます。
どちらも女性ホルモンの分泌に異常をきたしている可能性があるため、長期間頻発月経もしくは稀発月経が続く場合は婦人科への受診をおすすめします。
- 生理周期がバラバラ
毎回の生理周期に7日以上ずれがある場合は「生理不順」とみなされます。
ただし10代は身体が成熟しきっておらず、生理周期が安定しないことも少なくないため、気にしすぎる必要はありません。20代以上もストレスや生活環境の変化でホルモンが一時的に乱れることがあるので、2~3ヶ月の生理不順であればそこまで大きな心配はいらないでしょう。
長期間(60日以上)月経が来ない場合や、20代以上で生理周期のバラつきが続く場合は婦人科を受診しましょう。
- 生理期間が長い・短い
生理期間が1~2日の場合は「過短月経」、8日以上の場合は「過長月経」と呼びます。
こちらも女性ホルモンの分泌に異常が出ている可能性があるため注意が必要です。
- 経血が多い・少ない
1回の生理あたり20~140mLが経血の正常な量であるといわれています。
経血が多い、レバー状の経血が出る場合は子宮筋腫・支給腺筋症などの可能性があります。またナプキンがほとんど必要ないほど経血が少ない場合も子宮発育不全などの病気が隠れていることがあるため、こちらも一度受診をおすすめします。
7.まとめ
生理周期は生理期(月経期)→卵胞(キラキラ期)→排卵期→黄体期(アンバランス期)の周期で移り変わっていきます。
周期によって体調が変わるケースもありますので、可能な限り自身の生理周期を知っておくとよいでしょう。基礎体温の数値変化から生理周期を把握する方法がおすすめです。特に妊活中の方は排卵のタイミングをつかめるため、ぜひ取り入れてみてください。
もし生理周期に乱れがあったり、生理前・生理中の身体の状態に異変を感じたりした場合は婦人科に相談してみましょう。

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。