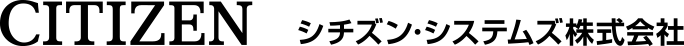高血圧の診断基準と分類|血圧別のリスクと対処法を解説
健康診断で「高血圧」と診断されたものの、どの程度のリスクがあるのか分からずに、なんとなく過ごしてしまう人は多いものですが、それは少々危険です。高血圧は時に命にもかかわります。
高血圧は一般の方でも重症度が分かる基準があるので、自分のリスクをしっかりと把握して適切な対処をしていきましょう。
今回は、高血圧の診断基準と重症度、基準値から分かるリスクや症状について解説します。対処方法も合わせてご紹介するので、早めに取り組みましょう。
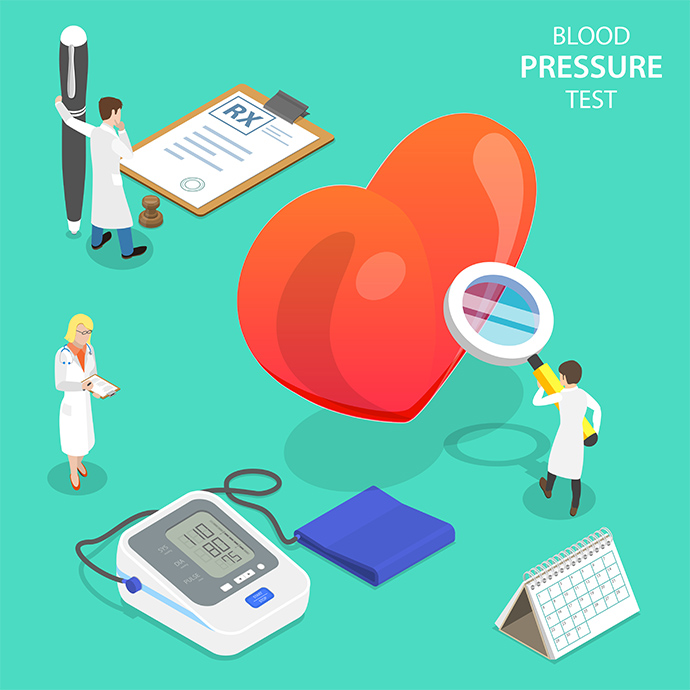
- 【目次】
- 2.高血圧の基準別にみるリスクや症状
- 高血圧のリスクは個人ごとに違う
- 高血圧のリスク
- 高血圧の症状
- 3.高血圧の治療法や対処方法
- 生活習慣を改善する
- 降圧剤などの投薬治療を受ける
- 家庭血圧を測って記録する
1.高血圧の診断基準と重症度
まずは高血圧の診断基準と重症度から解説します。高血圧と診断される数値と治療の緊急度をみていきましょう。世界保健機関/国際高血圧学会(WHO/ISH、1999年)では高血圧とその重症度を以下のように分類しています。
<血圧レベルの定義と分類>
| 分類 | 収縮期血圧 (mmHg) |
拡張期血圧 (mmHg) |
重症度 | 最適な | <120 | <80 | 最も理想的な血圧 |
| 普通 | <130 | <85 | 健康な血圧 |
| 正常高値 | 130-139 | 85-89 | 生活習慣の改善が必要 |
| グレード1の高血圧(軽度) | 140-159 | 90-99 | 生活習慣の改善や薬物治療が必要 |
| グレード2の高血圧(中等度) | 160-179 | 100-109 | 早急な治療が必要 |
| グレード3の高血圧(重度) | ≧180 | ≧110 | 直ちに治療が必要 |
| 孤立性収縮期高血圧 | ≧140 | <90 |
※参照:1999年 世界保健機関±国際学会高血圧管理ガイドライン
1999-Nen sekai hoken kikan ± kokusai gakkai kōketsuatsu kanri gaidorain kōketsuatsu gaidorain bunka-kai
日本の医療現場では、120-129かつ<80は「正常高値血圧」、130-139かつ80-89は「高値血圧」として生活改善を指導される場合があります。上記の血圧基準より低い数値であっても個人が持つリスクによっては危険があるということです。数値に油断せず注意していきましょう。
診察室では緊張状態や計測時の時間帯などによって、数値が正確に出ない場合があります。健康診断などの数値に油断せず、家庭でも血圧測定を行うことが大切です。
また高齢者は加齢による動脈硬化の影響で、上の血圧だけ高い孤立性収縮期高血圧になりやすいので注意しましょう。
2.高血圧の基準別にみるリスクや症状
高血圧はそれ自体にも症状がでますが、重大な疾患のリスクを高めるのが怖いところです。また個人差が大きいことでも知られるので、あの人は大丈夫だったからと油断してはいけません。
高血圧のリスクは個人ごとに違う
高血圧のリスクの高さは数値だけで決まるものではありません。同じ血圧でも、その人の年齢や持病、生活習慣などによってひとりひとり変わります。世界保健機関/国際高血圧学会(WHO/ISH、1999年)によるリスク分類は以下の通りです。
<高血圧のリスク層別化>
| 他のリスク因子及び病歴 | グレード1 収縮期血圧140-159または 拡張期血圧90-99 |
グレード2 収縮期血圧160-179または 拡張期血圧100-109 |
グレード3 収縮期血圧≧180または 拡張期血圧≧110 |
| Ⅰ:他にリスク因子なし | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |
| Ⅱ:リスク因子1-2個 | 中等リスク | 中等リスク | 特に高リスク |
| Ⅲ:リスク因子3個以上 または標的臓器障害・ 循環器関連合併症 |
高リスク | 高リスク | 特に高リスク |
| Ⅳ:ACC(肺胞細胞癌・ 陽極性閉鎖筋収縮) |
特に高リスク | 特に高リスク | 特に高リスク |
参考:※参照:1999年 世界保健機関±国際学会高血圧管理ガイドライン
1999-Nen sekai hoken kikan ± kokusai gakkai kōketsuatsu kanri gaidorain kōketsuatsu gaidorain bunka-kai
「リスク因子」とは危険な状態になる確率を高める要因のことです。高血圧では年齢の高さや持病、喫煙、肥満などがそれにあたり、同じ血圧値であってもその人が持つリスク因子の数によって危険度が変わります。
例えば、グレード1の高血圧では「Ⅰ:他にリスク因子なし」に該当する健康な若い人であればそれほどリスクは高くありませんが、65歳以上で肥満と糖尿病がある方は「Ⅲ:リスク因子3個以上」に当たり、重症化リスクはかなり高くなります。
高血圧のリスク
高血圧のリスクは様々ですが、動脈硬化の原因になり、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気を発症することも少なくありません。また、腎機能が低下し透析が必要になるケースもあります。
高血圧の症状
高血圧の症状は自覚しにくく、知らないうちに症状が進行している場合も珍しくありません。以下のような症状が現れたら放置せずに診察を受けましょう。
早朝の頭痛、めまい、耳鳴り、頭重感、首の張り、肩こり、のぼせ、息切れ、動悸、発汗、手足の冷えなど
3.高血圧の治療法や対処方法
高血圧と診断されたらどのように対処すればいいのでしょうか?重症度や体質、生活習慣などによって方針は変わるようですが、一般的には以下のような治療法が取られます。
生活習慣を改善する
高血圧の改善で最も重要なのは生活習慣の見直しです。健康な食生活、節酒、禁煙、体重管理、適度な運動の5つに取り組んでいきましょう。
- 食塩制限6g未満を目指す
- 野菜や果物を積極的に摂取する
- 飽和脂肪酸、コレステロールの摂取を控える
- 多価不飽和脂肪酸、低脂肪乳製品を積極的に摂取する
- お酒はビール中瓶1本または日本酒1合または焼酎0.5合程度まで
- 禁煙する
- 適正体重(BMI25未満)を目指すまたは維持する
- 軽度の有酸素運動を毎日30分または週180分以上行う
家庭血圧を測って記録する
血圧は診察室では緊張で正確に測れない場合がある上、一日の中でも変動するため毎日自宅で血圧を測ることが重要です。以下のポイントを守りながら毎日計測して記録しましょう。
- 朝と夜の1日2回、決まった時間帯に測る。
- 入浴後や運動後などは避けて安静時に測る。
- 毎回同じ姿勢で座って測る。
降圧剤などの投薬治療を受ける
高血圧の重症度や個人が持つリスクに応じて、降圧剤が処方される場合もあります。降圧剤には利尿剤、血管拡張薬 、神経遮断薬、神経遮断薬などいくつかの種類があり、医師がその時の体調や症状に合わせて処方します。
他の家族に処方された薬やずいぶん前の飲み残しなどを自己判断で飲むと危険なので、注意しましょう。
4.血圧の検査結果が正常値でも油断は禁物
血圧の検査結果が正常値内でも油断は禁物です。血圧は測る時間帯や環境、ストレスなどの影響で変わりやすいため、「健康診断では血圧に問題なかったのに実は高血圧だった」という症例は珍しくありません。
自覚症状も少ないため、高血圧に気が付かないうちに血管や心臓、脳などに負担をかけ、脳梗塞を突然引きおこすというようなケースも多くみられます。
家庭血圧を記録する習慣を身に着けること。自分の血圧を正確に把握すること。日頃から食生活や飲酒、運動量にも注意することが大切です。
5.まとめ
高血圧は基準値ごとに重症度がわかるように分類されており、それに応じた治療や生活改善が必要です。
ただし、高血圧のリスクの大きさは数値だけでなく、個人の年齢や生活習慣、持病の有無によっても変わってきます。数値が低めでも油断せず対策しましょう。
高血圧の対策や治療方法は、食生活の見直しや運動、節酒、禁煙が基本です。必要に応じて医師から降圧剤が処方されます。そしてもっとも大切なのは家庭血圧の把握です。毎日2回決まった時間に計測して、自分の血圧を把握しておきましょう。
【参考】
1999年 世界保健機関±国際学会高血圧管理ガイドライン
1999-Nen sekai hoken kikan ± kokusai gakkai kōketsuatsu kanri gaidorain kōketsuatsu gaidorain bunka-kai
「高血圧-リスク分類」(川田クリニック)
https://kawataclinic.jp/%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%9C%A7
「高血圧」(鈴木内科クリニック)
https://suzukinaika-cl.com/highbloodpressure/
「高血圧」大阪がん循環器病予防センター
http://www.osaka-ganjun.jp/health/cvd/hypertension.html

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。