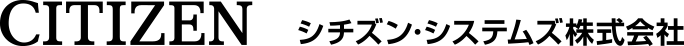運動による消費エネルギーの計算方法は?
健康維持・減量に最適な運動量を解説
「最近体重が増えてきて気になる」「健康的に減量しながら体力をつけたい」という方は、適度な運動を含む日常生活の改善を行うのが一番効果的でしょう。
ケガをせず長く続けるためにはウォーキングなどの軽い運動から始めることをおすすめしますが、目標によっては強度の高い運動を取り入れた方がよい場合もあります。運動ごとの消費エネルギー量を知り、自分に合った形で日々の生活に運動を取り入れましょう。

- 【目次】
- 1.運動による消費エネルギー量を計算する方法
- ①運動の強度=メッツを調べる
- ②体重・時間とかけあわせる
- 2.健康を保てる運動量の目安は?
- 生活習慣病予防に効果的な運動量
- 具体的な運動量の目安
- 3.減量に必要な消費エネルギー量を調べる方法
- 1kgを減らすには約7,000kcal消費する
- 減量後の体重から逆算して運動量を決める
- 4.ウォーキングで効率よく消費エネルギーを増やすコツ
- 早歩きする時間を作る
- 慣れてきたら中強度の運動を取り入れる
1.運動による消費エネルギー量を計算する方法
消費エネルギーとは、人間が生きていく上で必要な生命維持活動や運動などで消費される体内のエネルギー量のことです。
運動の強度によって消費エネルギー量が異なるため、まずは運動ごとに設定されている強度を調べて消費エネルギーを計算してみましょう。具体的には以下の手順で行います。
①運動の強度=メッツを調べる
運動ごとの強度を調べるにはメッツ(Mets)と呼ばれる単位から計算する必要があります。
メッツは安静時(静かに座っている状態)を1メッツとしてその何倍のエネルギーを消費するか、すなわち身体活動の強度を表しています。
主要な運動のメッツ
| ウォーキング(普通歩行)、バレーボール、ピラティス | 3.0メッツ |
| ほどほどの強度で行う筋トレ | 3.8メッツ |
| テニス(ダブルス)、中等度の水中歩行 | 4.5メッツ |
| 速歩、野球、ソフトボール、スクワット | 5メッツ |
| バドミントン | 5.5メッツ |
| ゆっくりとしたジョギング、高強度のウェイトトレーニング、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) | 6.0メッツ |
| ジョギング、サッカー、ハンドボール | 7.0メッツ |
| エアロビクス、テニス(シングルス) | 7.3メッツ |
| サイクリング、激しい強度で行う筋トレ | 8.0メッツ |
| ランニング(139m/分) | 9.0メッツ |
②体重・時間とかけあわせる
身体活動によるエネルギー消費量(kcal)は、メッツ×時間(h)×体重(kg)で推定することができます。
(例)体重60kgの人が1時間ウォーキングした場合の消費エネルギー
3.0メッツx1時間x60kg=180kcal
2.健康を保てる運動量の目安は?
減量に必要な消費エネルギーを知る前に、健康維持に必要な運動量の目安を知っておくことが重要です。体力に自信がない方はまず健康的な運動量を目指して習慣を改善していきましょう。
生活習慣病予防に効果的な運動量
身体活動量が多いほど生活習慣病などの発症・死亡リスクが低下するため、健康維持には適度な運動が非常に大切だと言えます。
適切な運動量を計算するには「メッツ・時」を利用すると便利です。メッツ・時とは運動の強度を表すメッツに実施時間をかけあわせた身体活動の量を示す単位で、普段の運動をメッツ・時に換算することで普段の運動量を計算することができます。
例えば、休みの日に2時間野球を行ったとしましょう。野球の運動強度は5メッツなので、5メッツ×2時間=10メッツ・時の運動に取り組んだことになります。
厚生労働省によれば、週あたり22.5メッツ・時以上の運動によって生活習慣病の予防が期待できるという研究結果が出ています。研究結果をもとに、歩行と同等にあたる「3メッツ」以上の運動を週に23メッツ・時程度行うことが推奨されています。
具体的な運動量の目安
「3メッツ以上の運動を週あたり23メッツ・時」という基準はイメージが付きづらいと思いますので、具体的な運動に置き換えて考えてみましょう。
歩行で例えると毎日60分以上歩くと達成される数値です。週あたり23メッツ・時という活動量は歩数に換算すると1日あたり約8,000歩以上歩いた場合とほぼ同等です。歩行より強度の低い家事などの生活活動は歩数換算すると1日あたり約2,000歩に相当しますので、残りの約6,000歩分、つまり1日あたり60分歩行すれば基準に達するという計算です。
60kgの人が週に23メッツ・時の運動を行ったとすると、1,380kcalのエネルギーを消費することになります。
また、歩行とは別に「息が弾み汗をかく程度」の運動を週4メッツ・時を週60分以上、筋トレを週2~3日行うことも同じく推奨されています。まとめると「1日60分以上歩く」「週60分以上筋トレなどの運動をする」この二つを達成すれば健康を保つための基準をクリアしていると言えるでしょう。
3.減量に必要な消費エネルギー量を調べる方法
スタイルを絞りたい、医者に減量するよう言われている場合は、健康維持に必要な量よりも多くエネルギーを消費しなければならないことが多いでしょう。
減量を目指す場合はあらかじめ消費エネルギーを計算し、運動ごとのメッツから逆算して具体的な運動量を求めるのがおすすめです。
1kgを減らすには約7,000kcal消費する
厚生労働省の資料によれば、体脂肪1kgを減らすために約7,000kcalが必要になります。
減らしたい体重から消費エネルギーを割り出せば、求められる運動量が見えてきます。
減量後の体重から逆算して運動量を決める
必要な運動量は現在の体重と減量後の目標体重からおおよそ求めることができます。
肥満度の判定と目標体重の設定にはBMI(Body Mass Index)=[体重(kg)]÷[身長(m)2]を用いるとよいでしょう。
例えば、155cm、63kgの人が減量を行うと仮定します。この場合、[体重(kg)]÷[身長(m)2]にあてはめるとBMIは約26.2で肥満(1度)に分類されます。日本肥満学会の基準で普通体重の上限値とされるBMI25.0は同じ身長だと約60kgなので、普通体重になるためには3kg以上減量が必要です。
体脂肪1kgを減らすために約7,000kcal必要になるため、3kgの減量には約21,000kcalのエネルギー消費を行うべきだと求められます。
3ヶ月かけて減量を行うとすると、1ヶ月あたりの消費エネルギーは約7,000kcal。
メッツの計算を用いて63kg時点での運動量に換算すると、
歩行1日60分→3.0メッツx1時間x63kg×30日=約5,670kcal/月
強度の高い筋トレ1日30分×週2(月8回)→8.0メッツ×0.5時間×63kg×月8回=約2,016kcal/月
→合計約7,686kcal
このような形で運動量を設定すると、具体的に目標が見えてきてモチベーションが高まります。
なお、食事から摂取するエネルギーが多いとその分必要な消費エネルギーも増えてしまうため、減量は適度な食事制限と並行して行うことをおすすめします。
4.ウォーキングで効率よく消費エネルギーを増やすコツ
運動量をあらかじめ計算して目標を立てることもよいモチベーションになりますが、自分にとって負荷の重すぎる運動を長期間続けることはできません。また、慣れない運動でケガをしてしまうリスクも高まります。
健康維持・減量には自分に合った運動量を無理せず維持し続けることが重要です。運動習慣がついていない人は毎日のウォーキングを増やし、効率的な歩き方を意識するのがおすすめです。
早歩きする時間を作る
通常の歩行が3メッツに相当するのに対して、早歩きした場合は4.3メッツになります。
健康的に生活するには1日あたり60分以上歩くことが推奨されています。60kgの人であれば60分歩いた場合の消費エネルギーは180kcalですが、早歩きなら同じ時間で258kcal。運動の効率は約1.4倍になります。
全てでなくとも「家から駅までは早歩きで移動する」など心がけてみると効率よく消費エネルギーを増やすことができるでしょう。
慣れてきたら中強度の運動を取り入れる
脂肪燃焼には週あたり10メッツ・時の有酸素運動を取り入れるとよいことが報告されています。
効率的な燃焼にはジョギング、サイクリングなど中強度の運動を比較的長めに行うのがおすすめです。ウォーキングも低強度ではありますが有酸素運動としての効果もきちんとあるため、組み合わせて取り入れることで効果を高めることができます。
5.まとめ
運動による消費エネルギーを調べるにはメッツを使うと便利です。
1週間あたりに必要な活動量は約23メッツ・時。1日のウォーキングであれば3.0メッツx1時間x体重で算出できる消費エネルギーを目指しましょう。また、健康維持ではなく減量を目指す場合は1kgの減量につき7,000kcalを目指すとよいでしょう。
自分に合った運動で健康的な体を目指しましょう。
【参考サイト】
健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf
改訂版
『身体活動のメッツ(METs)表』(国立健康・栄養研究所)
https://www.nibiohn.go.jp/files/2011mets.pdf
BMIの基準(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-02-001.html
有酸素運動について(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-05-002.html

- 錦 惠那 先生
- 【保有資格】
- 内科専門医、産業医
- 【プロフィール】
-
関西圏の医学部卒業。現在は内科医として市中病院で診療を行っている。
腎臓病、透析医療を専門分野とし、産業医としても活動している。病気の予防は治療と同等に重要であり、予防医学の理解を深めてもらうため、病気やヘルスケア情報の発信にも取り組んでいる。
私生活では1児の母でもあり、日々育児にも奮闘している。