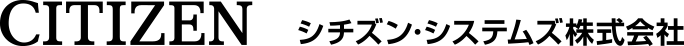るい痩とは?診断基準や原因、対処法について解説
特別なことは何もしていないのに短期間で急激にやせると、不安になってしまいますよね。体重の減り方が不自然なときは、「るい痩(るいそう)」の可能性があるので注意が必要です。
るい痩という聞き慣れない用語に、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、るい痩は、正しい知識を持って行動すれば、予防や治療が可能です。
この記事では、るい痩の診断基準や原因、治療法や予防法などを解説します。

- 【目次】
- 2.るい痩の原因
- 食事量の減少
- 消化機能の障害
- 内分泌障害・代謝障害
- 代謝の亢進
- 栄養分の喪失
1.るい痩とは?病的な「やせ」とされる診断基準
るい痩(るいそう)とは、体重が著しく減少した病的な「やせ」の状態を指します。以下のいずれかに該当すると、るい痩と診断されます。
- 標準体重を20%以上下回る
- 6カ月以内に10%以上の体重減少がある
- BMIで17kg/m2以下
標準体重は以下の式で計算します。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
例えば、身長160㎝の人がるい痩と診断される体重は、標準体重を元に計算すると45kg以下が目安となります。
1.6(m)×1.6(m)×22=56.3kg
56.3kg×20%=11.26kg
56.3kg-11.26kg=45.04kg
2.るい痩の原因
るい痩を発症する主な原因は以下の5つが考えられます。
- 食事量の減少
まず考えられる原因として、食事量の減少があります。例えば、貧困や災害といった環境的要因や、摂食障害などが背景にあると考えられます。
薬の副作用による食欲不振や、高齢者であれば、むせたり、飲み込みが難しくなったりする嚥下障害で、食事量が減る場合もあるでしょう。
また、偏食が原因で、必要な栄養素の摂取量が不足し、るい痩につながるケースもあります。
- 消化機能の障害
消化機能の障害も、るい痩の原因となります。
例えば、食道がんや胃がんなどの消化管の病気・異常により、消化と吸収いずれかの機能に障害が生じると、るい痩につながる可能性があります。
潰瘍性大腸炎のような、炎症系の腸疾患も、消化機能の障害を引き起こします。膵がんなど、膵臓に異常がある場合にも、食物の吸収が難しくなり、るい痩になる場合があります。
- 内分泌障害・代謝障害
内分泌障害や、代謝障害もるい痩の原因となります。これらは「栄養素の利用障害」とも呼ばれ、取り込んだ栄養を体内の組織で利用できなくなります。
例えば、糖尿病などの内分泌障害では、インスリンの不足により、血液中のブドウ糖を細胞に取り込めません。
肝硬変などの代謝障害では、代謝をつかさどる肝臓が、摂取した栄養をうまく利用できなくなってしまいます。
- 代謝の亢進
代謝の亢進(こうしん)により、るい痩となるケースもあります。亢進とは、何らかの異常によって本来の働きよりも必要以上に活発化してしまうことです。
結核やがん、バセドウ病などの疾患は、代謝の亢進を引き起こします。代謝が亢進すると大量のエネルギーが消費され、やせが進行しやすくなります。
- 栄養分の喪失
栄養分の喪失から、るい痩が引き起こされるケースもあります。
例えば、がんではがん細胞が増殖して正常組織が破壊されたり、がん細胞そのものが壊死したりすることで、体の構成成分であるたんぱく質が失われます。
ほかにも、広範囲のやけどや手術の際には、たんぱく質が多く含まれる滲出液(しんしゅつえき)が大量に排出されます。このような場合も、たんぱく質の喪失により、るい痩が引き起こされる可能性があります。
3.るい痩の治療
るい痩の治療は、原因やその人の体の状態や持病などによって異なりますが、主な治療方針としては次のようなものが考えられます。
るい痩の原因となるような基礎疾患がある場合には、まずその治療を優先して行います。
ベースに低栄養状態がある場合には、内服薬で食欲を増進させるほか、不足している栄養を補います。飲み物やゼリーといった、摂取しやすい栄養補助食品でエネルギー量を増やす方法や、点滴などによる栄養摂取の方法も候補となります。
高齢者などで、食べ物を飲み込みにくいといった嚥下障害がある場合には、ミキサー食などの介護食の検討もされます。
4.「やせ」から「るい痩」への進行を予防する方法
「やせ」から「るい痩」への進行は予防することが可能です。
大前提として、体重が減るメカニズムを知っておきましょう。消費エネルギーが摂取エネルギーを上回ると、不足分を補うために脂肪を燃焼させたり、たんぱく質を分解したりして体重が減少します。
るい痩を予防するためには、食欲や食事量が低下していないかをこまめにチェックし、体重減少が起こりそうなサインを早めに察知して対処することが大切です。
また、やせが起きている時には、倦怠感や疲労感、皮膚の乾燥、口角炎・口内炎のほか、身体活動の低下などの症状もみられます。これらの症状が出ていないかどうかも、食欲と併せて、よく観察しなければなりません。
体組成計などで、日々の体重管理を行うことも大切です。いつから、どれくらいの期間をかけて体重が減っているのか、体重減少のペースはどうかなど、小さな変化に気づけるように、定期的な計測を行いましょう。
シチズン・システムズの体組成計(HMS323・HMS525)は、体重や体脂肪率、BMI、筋肉量や基礎代謝の計測もできます。乗るだけでBMI値が分かるので、るい痩の診断基準である「BMI値17kg/m2以下」との比較も簡単です。
また、体組成計HMS525は、目標体重の設定や100g単位の体重計測が可能なため、厳密な体重管理をしたい方にもおすすめです。前回の測定結果も確認できます。
4人分のユーザー登録もでき、乗るだけでユーザーを自動認識してくれるため、操作の手間が少なく、体重測定の習慣を継続しやすいでしょう。
5.まとめ
るい痩とは、体重が著しく減少した病的な「やせ」の状態です。標準体重を20%以上下回る、6カ月以内に10%以上の体重減少、BMI値17kg/m2以下が診断基準となります。
るい痩が起こる原因は、以下のようなケースが考えられます。
- 食事量の減少
- 消化機能の障害
- 内分泌障害・代謝障害
- 代謝の亢進
- 栄養分の喪失
るい痩の治療は、原因となる基礎疾患がある場合はその治療が最優先されます。そのほか、その人の体調、状態に合わせて内服薬や飲み物、ミキサー食などからの栄養摂取が主な治療法です。
るい痩への進行は予防できます。日頃から食欲・食事量の低下、やせの症状がないかをこまめに観察し、体組成計などでの体重測定の習慣を身につけましょう。もし体重減少のサインが見られたら早めに対処することが重要です。